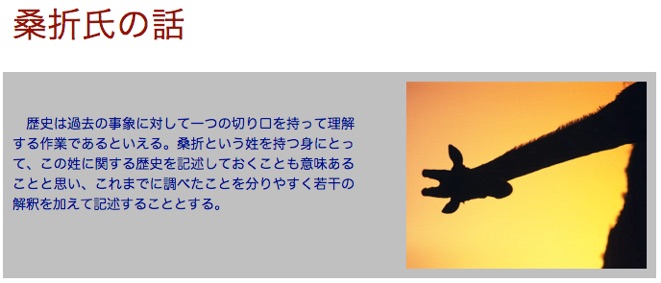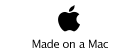桑折氏の話-5
<桑折氏と天文の乱>
桑折氏中興の祖は景長(貞長、宗茂とも)と名乗った10世と思われる。桑折家の家系図では最初の名が貞長、ついで景長、最後に宗茂となっている。タネ宗と同世代であるが、たね宗より20歳若い年代とされる。桑折家の家系図ではこの3人は同一人物とされているが、他の資料では別人とされていることもある。たね宗55歳のとき天文の乱が起こり、景長は35歳、次男竹鶴丸が生まれた直後となる。晴宗は10歳若い24歳とされる。
伊達正統世次考では景長は天文の乱の折に中野宗時と共に晴宗をそそのかしてたね宗と争う首謀者とされているが改名後の名前で記述していると思われる。鷹狩りを好み、朱鷺色の鷹を手に入れて織田信長に贈り、親交を築いたという逸話も残している。信長は奥州から献じられた鷹を終生高くかっていたとされるがそれがこの鷹であれば面白い。貞長は晴宗が奥州探題と成ったとき、守護代と成っており、永代の特典を多く得ている。晴宗が奥州探題となるのは天文の乱収束後と思われるので、この時点で貞長とすると天文の乱の首謀者を景長とする説の時間軸が合わないところがある。
織田信長に鷹を贈った逸話は晴宗の次の輝宗時代のものとされ、1572年とされる。この年景長は67歳であり、いささか年を食いすぎているように思われる。もっと若い時代、輝宗の時代に中野氏を追放し再び中央集権化していく過程で景長と改名したとも考えられる。中野宗時親子が謀反を起こし追放されるのは1570年なので60歳を越すことになる。いずれにしろ後に宗茂を名乗り、桑折家の家系では宗茂が正式の名称とされている。
最初が景長、天文の乱後に貞長、輝宗の時代に宗茂とするとすっきりするが、織田信長に鷹を贈って世に名をあらわしたとする記述とはそぐわない。また、桑折家の菩提寺である等覚寺(宇和島)の位牌によると初名貞長、次名景長とあり、景長は輝宗時代とも取れる。
天文の乱で桑折貞長は晴宗側の参謀として活動し、中野氏と共に晴宗側勝利の中核となった。この功により、一家の格になったとされる。所領内の徴税権を得、伊達氏は奥州探題、桑折氏は守護代に任命され、実力を持つこととなった。この時代の一族の席順が記されている記述が残っている。桑折氏は伊達氏と同盟を結ぶ相馬氏や大崎氏と同列の格と記されている。中野氏は後に謀反を起こしたとされ、失脚する。伊達家内の勢力争いでもあった天文の乱で活躍した桑折景長は家系によると大きな一族の変動を経験している。家系では宗茂が正式の名前として記されている。宗の字は伊達家の名称として知られ、一家として重く遇されてきた時期からは宗茂としたと考えられる。
景長の妻は石母田家の出であり、景長の長女は石母田家に嫁いでいる。長女の子は景頼と名づけられ、後に桑折左衛門となる。名前に景を入れているところを見ると、景長時代が活躍期だったのではないかと思われる。
<改名の時期>
桑折景長の時代は織田信長が実力者として台頭してきていた時代である。晴宗は家督を輝宗に譲っている。当時、織田信長との関係構築に際して、鷹好きの信長に鷹を贈ることを伊達家では計画していた。若い頃、鷹狩りを好んでいた景長は山にこもって松の木の下で鷹を見張り、朱鷺色の素晴らしい鷹を手に入れ、織田信長に献上し、親交を得たという逸話を残している。この時期、信長に近づき、同盟関係を得ようとしていたとされ、信長の礼状は伊達家に伝わっている。その後も信長へ鷹を贈った記録や信長からの「けしからぬ行動を取る上杉謙信への牽制依頼」などの書状が伊達家に残されている。
しかし、輝宗が朱鷺色の鷹を送っているのは1572年とされ景長は65歳を超えている。すでに35歳になっていた宗長(後の点了斉)の時代と思われる。あるいは構想を立てたということかも知れない。
晴宗の時代、天文の乱の後遺症もあり伊達家の勢力は大きく後退していたとされる。輝宗の代になって、再び中央集権に戻す動きが進む。中野氏は謀反の疑いで追放され、桑折貞長は景長と改名し、輝宗を支える形で進んだのではないかと思われる。次男の宗長(点了斉)は輝宗、政宗2代に渉って参謀を務めている。飯坂家に嫁いだ景長の次女の生んだ2人の娘の内長女は点了斉の息子政長に嫁し、次女は政宗の側室として秀宗を生んでいる。
景長時代の桑折氏は伊達の一家として一枚岩となっていたと考えるべきと思われる。宗茂と更に改名した理由は分らない。たね宗時代に景長、晴宗時代に貞長、輝宗時代に宗茂であればすっきりするが家系に残る順番と異なる。晴宗から貞長に宛てた席次などの資料の整合性も取れない。伊勢守、播磨守の名は9世の頃から使っているが、名乗っていた理由も調べ切れていない。
想定される経緯は貞長が最初の名、景長としたのは晴宗から輝宗に変わる頃、ここでも天文の乱の再来が懸念されたが、景長と改名した桑折は輝宗につく。このころが盛期で、孫には景の字をつける。晴宗と争うことになった輝宗にとって相談役的立場が景長だった可能性もあり得る。「鷹を贈って名をあらわした」のは輝宗でそのアドバイスと手助けをしたのが景長と考えるとつながるようにも思える。更に策動する中野を追放し、輝宗の信を得た後、宗の字を持つ宗茂と改名する。といったところが妥当なところか?
景長は1578年、72歳で亡くなっており、その6年後の1584年に輝宗は政宗に家督を譲って42歳で隠居する。
桑折略記によると宇和島の等覚寺の桑折家の位牌は初代親長の次は10世宗茂になっている。確認してみるが、宇和島伊達藩創設時に桑折氏の墓は初代と宗茂以降を持って行ったと想定される。宇和島伊達家は秀宗に始まるが桑折家は宇和島にすべて持ってきたと言える。
上杉藩の米沢移転に際しても上杉の墓は移転しており、当時はこのようにしていたのだろう。